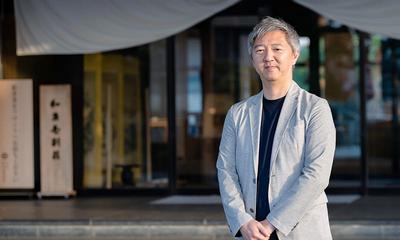リーダーたちの羅針盤
「ふすま」の伝統を守るため
強い使命感と柔軟な発想で挑み続ける
ハリマ産業株式会社
大久保 謙一代表取締役社長
1966年生まれ。大学卒業後、1990年に大日本印刷に入社し、営業として働く。98年、父が社長を務めるハリマ産業に入社し、営業経験を生かして新たな販路となるハウスメーカーの開拓に注力する。2008年に代表取締役社長に就任。21年より海外展開をスタートし、25年2月、フランス・パリのふすま展示会に参加。
- ハリマ産業
- 大久保謙一
- ふすまメーカー
- 天皇陛下
- 海外市場開拓
この記事のポイント
- 千葉県松戸市でふすまをはじめ建具を製造するメーカー、ハリマ産業の大久保社長
- 住宅から和室が減り、主軸のふすまの需要が減少。事業継続に危機感が生まれる
- 行幸をきっかけに奮起。海外展開をはじめ新たな事業展開でふすまの普及に努める
大久保謙一社長が父からふすまメーカーのハリマ産業を引き継いだとき、経営は赤字続きだった。ふすま自体の需要が落ち込んでいたからだ。会社存続のため、ふすまを後世に伝えるため、新たな販路開拓・新たな事業への着手に積極的に取り組んだ。

職人が一人でこなしてきた作業を分業化し、短期間での技術習得を可能にしたことで生産性を向上させた
ハリマ産業は、和室の仕切りとして使われるふすまのメーカーです。
創業は1970年、私の父が立ち上げました。父はもともと銀行員でしたが、兵庫県でふすま製造をしていた父の実兄から勧められて起業を決意したそうです。
創業当時は住宅着工ラッシュで、ふすまの需要は旺盛でした。ふすまメーカーの多くは江戸時代から続く老舗が多く、ハリマ産業は最後発でした。父は「工程ばらし」という、ふすまの製造過程を4つに分解し各工程の無駄を見直し生産性を向上させる手法で売り上げを伸ばしました。
それまでのふすま製造は、熟練した職人が工程の全てを一貫して作業するのが当たり前でしたが、工程ばらしにより、職人にはふすま製造の工程の一部分だけを担当してもらえば済むようになりました。そうすると、すぐに仕事を覚えられ、熟練も早くなります。素人でも製造に携われるようになったのが最大の特徴です。パート社員でも早期に現場を任せられて、旺盛な需要に応えられました。加えて問屋を介さず、顧客と直に取引するように販路を見直しました。その結果、製造から取り付け工事までを一貫して行え、顧客の多様なニーズに応えられるようになりました。
そんな順風満帆ともいえる会社でしたが、子どもの頃に「家業は継がなくて良い」と言われていたため、社長になるとは全く想像していませんでした。大学卒業後は大日本印刷で営業職に就き、ずっとその仕事を続けていくつもりでした。しかし8年ほど勤めた頃に父が病に倒れ、急きょ家業を手伝うことになりました。
当初はかなり経営を楽観視していました。当時のハリマ産業は、年商7億円ほどの会社でした。私は大日本印刷の営業として年間6億円ほどのノルマを抱え、それを達成し続けていた。金額規模がそれほど大きいと感じなかったからです。しかしハリマ産業に入社して、経営が相当厳しい状態だと知りました。新築マンションは増えても、和室が減り、ふすまのニーズは縮小傾向にありました。新築マンションの仕事が受注できても、プロジェクトが終わるとゼネコンとの関係も終わります。次のマンションの仕事を受注するには、新たなコンペに参加しなければなりません。価格が安いところに決まってしまう傾向も強まっていました。
この状況を打破するために、私が注目したのはハウスメーカーでした。マンションで売り上げが確保しづらくなり、その頃業績が堅調だったハウスメーカーに販路を拡大しようと考えました。それまで取引はなかったものの、前職で培った営業スキルを生かして新規開拓を進めました。
天皇陛下の行幸が大きな転機に
私が入社した10年後に父が亡くなり、そのタイミングで社長に就任しました。
ハウスメーカーへの販路拡大で経営は多少持ち直したものの、決して安泰ではありませんでした。和室が減ってふすま需要も減退したところに、戸建てそのもののニーズ減少が追い打ちをかけた。頼みの綱だったハウスメーカーからの仕事も減り、徐々に経営は厳しくなっていきました。
ふすま業界に関する明るい話題がない。将来が見えない。このままでは会社が危ないと危機感を覚えました。ふすま事業から手を引くことも真剣に考えました。工場を利用して学習塾や葬儀場にする案や、印刷会社に転じる案も具体的に検討しました。それほど追い込まれていたのです。

天皇陛下の行幸で強い使命感が生まれ、ふすまメーカーとして継続する決意を固めた
そんな折、大きな転機が訪れました。ハリマ産業が天皇(現・上皇)陛下行幸の栄誉を賜ったのです。
天皇陛下は以前から定期的に日本の中小企業のご視察をされており、当社に行幸されたのは2005年のことでした。陛下はふすまの製造工程を興味深く視察され、ふすまの歴史と伝統を守る当社の姿勢に対し、温かい励ましの言葉をくださいました。社員一同、感激で胸が熱くなったのを今でも鮮明に覚えています。
この日を境に、全社員がふすまメーカーとしての自信を取り戻した気がします。「当社はもう必要とされていないのだろうか」という状況から、「陛下にご視察いただける特別な事業を手掛ける会社なのだ」と意識が変わり前を向けたのです。歴史と伝統あるふすまを、我々が守らなければならない。強い使命感を覚えた契機となったのです。
畳店と手を組み、ドアにも着手
ふすまの事業を継続するには、会社の立て直しが急務でした。そこで始めたのが、畳メーカーとの連携とドア事業への着手です。
九州のある畳メーカーが、自社でふすまの取り扱いを始め収益を伸ばしていると知りました。ゼネコンもハウスメーカーも、畳とふすまを別々の会社に発注するより、1社に任せた方が効率的です。やがてそのやり方をまねる畳メーカーが増え、九州から関西、中部へと広まり、その流れは関東にも押し寄せました。
普通であれば畳メーカーに仕事を奪われると危機感を抱くところですが、我々はその流れに乗ることを選びました。畳メーカーと手を組んだのです。
当社にはふすま製造の技術と生産体制がある。質の良い製品を安定的に供給できます。畳メーカーにとっても、高品質なふすま提供ができれば優位性が生まれ、当社と手を組むメリットが生じます。畳メーカーにはできない「ふすまの張り替え」も対応可能になります。当社としては、新たな販路を開拓でき、売り上げを増やせます。双方にメリットがあったのです。
一方で、住宅における和室の減少傾向は変わりませんでした。そんなとき「ハリマさん、ドアは作れない?」と声が掛かったのです。実は、当社にはドアを作る機械がありました。創業した頃、ふすま用の製造機械が手に入らず、父がドア用の製造機械を改良して、ふすま製造を行っていたのです。この機械を元に戻しドアの製造が行えるようにした結果、さらに収益を安定させることができました。
振り返れば、天皇陛下の行幸前は、ふすまメーカーというプライドにこだわり過ぎていたのかもしれません。同業者とは組まない、問屋を間に入れない、ふすま以外はやらない。足かせとなるルールを設け、自らの首を絞めていた気がします。しかし、「ふすまを守るために会社を守る」と考えを切り替えられた。発想が柔軟になり、どんなニーズにも対応するようになりました。収益のため、背に腹は代えられない事情があった結果、新たなニーズを掘り起こせたり新規の顧客を紹介いただいたり、着実にビジネスが広がったと感じます。
仏・パレロワイヤルにふすまを

海外市場の開拓は事業を存続させるため。その先には日本国内の需要拡大という目標がある
ドア製造が新たな収益の柱となりつつあるものの、本業はふすまです。会社の収益を確保しながらも、ふすまの普及にも地道に取り組んでいます。
21年からチャレンジしているのが、海外市場の開拓です。取引金融機関である商工組合中央金庫から、海外展開ハンズオン支援(海外ビジネスを目指す中小企業に向けてアドバイスを行うサービス)の紹介を受け、現在、日本文化に対する関心が高いフランスでの販路開拓に取り組んでいます。
国内において、ふすまを取り巻く環境は厳しさを増し、特に欄間や障子はふすまよりも前に需要低下が顕著な状況でした。いずれも、一般的な住宅で採用されるケースはほとんどなくなってしまった。ですが調べてみると、一部の欄間や障子メーカーが海外に進出して売り上げを伸ばしているのが分かりました。「ふすまも行けるのではないか」。リサーチを行い、欄間、障子が多く売れているフランスに照準を絞りました。
ただ、ふすまは取り付ける場所=敷居があって初めて成り立つものです。欄間も障子も、海外では壁にそのまま張り付けてインテリアとして扱われています。ふすまはスライドさせて使う。スライドさせるためには室内に敷居を取り付けなくてはならない。難易度は高いと考えました。
それでも、欄間、障子が受け入れられているフランスならば、商機があるかもしれない。現地のニーズを探り、どんなものなら受け入れられるのかを考え抜きました。カラフルなふすま紙を貼ったアート作品はどうか。市場の反応は鈍く、フランス人はより「本物」を求めている。その結果、シンプルなふすまのままで真っ向勝負すると腹をくくりました。
まずは、現地のインテリアショップとパートナーシップを組み、ショールームにふすまを置いてもらうことに成功しました。そして、ホームページをフランス向けに改編したところ、ネット経由で予想もしない大仕事を受注することになりました。フランスの歴史的建造物であるパレロワイヤルの1室に、我々のふすまが入ることになったのです。日本文化が好きだという現地の人が画家に絵を描いてもらい、それをふすまにしてくれる業者を探していたとのこと。予想もしなかったニーズに、本当に驚かされました。この受注を機に、現地での信用が生まれ、少しずつ問い合わせが来るようになりました。
とはいえ、このまま海外のビジネスに大きくかじを切ろうとは思っていません。当社の目指すべき目標はあくまで日本国内での需要拡大で、海外展開はそのためのステップだと考えているからです。
例えば日本の伝統的な南部鉄器は、現在フランスで大人気です。ただし、昔ながらの黒色の鉄器ではなく、内側をほうろう加工された上に外側は赤やピンク、青などカラフルな色で塗られたものになっています。丈夫で冷めにくい実用性の高さに、モダンなたたずまいが相まって人気を集めている。南部鉄器をほうろうでコーティングする発想は、我々では到底思い付きません。しかも、逆輸入された日本でも注目を集めています。
ふすまも海外展開することで、南部鉄器のように思いもよらない形に生まれ変わるかもしれない。部屋を仕切る用途以外にも、意外な使われ方をするかもしれません。想定外のイノベーションが起こり、結果的に日本での需要喚起につながればと期待しています。
休みが取りやすい環境を整備
海外進出というと華々しく聞こえるかもしれませんが、当社は社員数20人程度の小さな会社です。会社として順風満帆とは言えないかもしれないが、社員全員がふすまに誇りをもって働いている。それが当社の一番の強みだと思っています。
特に中小企業では人材不足がかなり深刻化しています。そんな環境下でも、当社の製造現場では女性パート社員が数多く活躍しています。工程ばらしによる分業制は、短期間で熟練できるメリット創出にとどまらず、時間に制約のある主婦が働ける環境をつくり、人材難の中でも人手を確保できる効果を出しています。
イキイキと働いてもらうため、休めるときには休むことを推奨しています。年間の休日134日は、中小企業の中ではかなり多いといえます。
ちなみに7月15日は、行幸を記念して公休にしています。天皇陛下がいらしてくださったことで、当社は失っていた自信を取り戻し、前向きな一歩を踏み出せた。その気持ちを忘れないために、この休みを大切にしています。取引先にも「またこの日がやって来たね」と言われるほど浸透し、当社のブランド力にもつながっていると感じます。
高いモチベーションをもって頑張ってくれる社員のためにも、ふすまを守り、魅力を伝え続けたい。これからも柔軟な姿勢で何にでも挑戦して、会社を存続させ続けたいと思っています。
動画を見る
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り2908文字 / 全文5316文字

企業情報
- 社名
- ハリマ産業株式会社
- 事業内容
- 和室・洋室向けの木製建具(ふすま、戸ぶすま、障子、各種ドア)の製造、販売、取り付け工事。リフォーム現場向けの建具の製造、特殊加工、取り付け工事
- 本社所在地
- 千葉県松戸市松戸新田129番地1
- 代表者
- 大久保謙一
- 従業員数
- 20名(2025年4月現在)