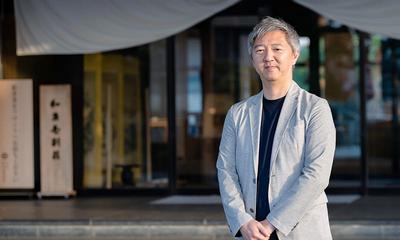リーダーたちの羅針盤
多様性を生かす経営で
世界が注目する企業へ
大橋運輸株式会社
鍋嶋 洋行代表取締役社長
大学卒業後、地元の信用金庫に7年勤務。その後、妻の祖父が創業した大橋運輸に1998年に入社し、同年11月に代表取締役社長に就任。地域に根差した運輸業を提供しながら、健康経営や社員のモチベーション向上、ダイバーシティー経営にも取り組む。経済産業省の「新・ダイバーシティー経営企業100選プライム」の中小企業初の受賞、5年連続で厚生労働省の「健康経営優良法人ブライト500」を受賞するなど健康経営やダイバーシティー経営に関する様々な賞を受賞。
- 地域密着型
- 健康経営
- ダイバーシティー経営
- ユーモア経営
この記事のポイント
- 金融業界から異例の物流業界へ転職、逆境をはねのけ改革を進める
- 健康経営と脱・下請けで、ES(従業員満足度)を高める
- 地域密着型のビジネスで社員のモチベーションをアップ
1954年、愛知県瀬戸市に創業した大橋運輸を、鍋嶋洋行社長は義父から受け継いだ。
社長就任時は赤字経営だった会社を、わずか2期で黒字に転換し、健康経営、ダイバーシティー経営など、独自の経営方針を次々と打ち出した。
原動力になったのは、大橋運輸を「人財を育てる企業にしたい」という熱い思いだった。
愛知県瀬戸市に本社を構える大橋運輸は、自動車のパーツや陶磁器の法人向けの輸送業と共に、引っ越しや生前・遺品整理など地域に密着した個人向けサービスを提供しています。1998年、私は大学卒業から7年間勤めた信用金庫を退職して、妻の父が社長を務める大橋運輸に入社しました。当時は、規制緩和で運送業界に進出する企業が増え価格競争が厳しく、大橋運輸の業績は大幅に悪化していました。入社を決めたのは、信用金庫で培ったノウハウを生かし、6期連続で赤字決算になった会社を立て直す手伝いをしたいと考えたからです。
入社してみると、同族経営で決算書に詳しい人材がいない。財務状況は最悪なのに、社内には大赤字に対する危機感がまったくありませんでした。そこで、「このままでは会社が危ない、私に任せてほしい」と義父を説得し、入社半年で私は社長に就任することになりました。
就任後、最初に手を付けたのは、「基本的なことをしっかりやる」です。身だしなみをきちんと整える、気持ちの良いあいさつをする、安全確認の指さし・声かけをしっかり行う。「当たり前のことでは?」と思われるかもしれません。ですが、その当たり前が実践できていない運送業者は、決して少なくない。基本を徹底すれば他社との差別化を図れる。気持ち良く荷物を受け取ってもらえれば、お客さまの信頼を得られると考えました。
従来型ビジネスモデルの変更も喫緊の課題でした。今でこそ弊社の下請け比率は3%以下になりましたが、当時は仕事の8割以上が大手企業の下請け業務でした。大手企業の下請け業務の場合、運輸会社に求められるのは価格と対応力です。価格が付加価値の状況では、社員の給料を上げられない。さらに大手企業の仕事は、入札が多く受注が安定しませんでした。
そこで、価格競争に巻き込まれないために、自分たちが発注元と直接取引する方向へシフトさせました。従業員には、「下請け仕事を減らして、利益率が高い仕事を増やす。短期的には売り上げが減るが、会社の将来につながる」と、今後の方針を伝えました。
運送業の付加価値は人がつくる
他社との差別化を図るには、付加価値向上への取り組みが必要です。運輸業界においても付加価値を生む源泉は、トラックではなく人です。真剣に仕事と向き合う人材を育てれば付加価値が高まり利益も増え、待遇を改善できるはずです。
ところが、「付加価値を高めれば、お金は後から付いてくる」と繰り返し伝えても、社員の意識はなかなか変わりません。「社員が一丸となって頑張ります!」という反応を期待したのに、「お金をくれたらやります」と厳しく突き返される始末でした。情けない思いを抱えて帰宅し、湯船で涙を流したこともありました。

職場環境改善と人材育成の目的で、女性社員を増員して健康経営やダイバーシティー経営に取り組みました
新しい取り組みへの反応は、たいがい不満や反発の声から始まります。のちに、短時間勤務で採用した女性社員を管理職として登用した際も、「短時間勤務なのに管理職なのか」「トラックに乗らないのに管理職なのか」と不満の声がありました。そんなときは、「今自分は、経営者としての判断を社員に試されている」と考えるようにしました。簡単に良い結果が出るなら、誰でもやろうと同意してくれる。結果がどうなるか分からないから否定される。それでも自分が心から大切だと思うなら、繰り返し言い続けるべきです。もし私が途中で言うのをやめれば、社員は「なんだ、その程度の気持ちだったのか」と思うでしょう。
人はそう簡単には変わらないと思います。社内の意識を変えるには、知識を高めることが大切です。継続的に社員に情報を伝えることで、知識が高まり意識も変わります。
悪戦苦闘する日々の中、社員のモチベーションが少しずつ上がり、前向きな発言もされるようになってきました。引っ越しサービスや生前整理など、企業が一般消費者にサービスを提供するBtoCの契約も増えた。社長就任2期目を迎え、大橋運輸は黒字経営に転換できたのです。
健康経営に乗り出す

健康経営の一環として社屋に設置する「高気圧O2ボックス」。社員は休憩時間に利用してリラックスできる
会社は黒字経営になったものの、私は5万円の中古軽自動車に乗って営業に駆け回り、不眠不休を続ける日々でした。結果、血圧が200を超え、体調を大きく崩してしまいました。そこから健康の意識が変わり、社員の健康経営に取り組みました。運輸業界にとって安全は大切ですが、健康あっての安全です。そして、共にいい習慣を身に付けることが大切です。
2018年から管理栄養士の資格を持つ女性社員を採用して、社内に相談窓口を設置。生活習慣病の予防や健康の保持・増進を目指して栄養や衛生管理の相談・指導を行いました。腸内環境を整える乳酸菌飲料や、地元の生産者から直接購入した安全・安心な野菜や果物を定期的に配布すること。社員だけでなく社員家族との交流も深まります。
運動不足解消のために、社屋の2階にトレーニングルームも造りました。空き時間に筋トレやストレッチを行える他、毎月勤務時間内にヨガ教室を外部講師が社員に指導しています。さらにトレーニングルーム内に疲労回復や睡眠の質向上に効果があるといわれる「高気圧O2ボックス」を設置し、健康状態維持に役立ててもらっています。25年2月から、採用条件に「禁煙者、または喫煙者であっても禁煙を約束する人」を加えた、禁煙採用も始めました。健康を意識すると、社員の安全意識も高まる。現在、健康経営のために使う年間1000万円の支出は、健全な事業経営に必要なコストだと考えています。
人材確保の鍵は多様性

国籍、性別、障害者や高齢者問わず多様な人材を登用し、社員一人ひとりに合わせた働き方をサポートする
少子高齢化社会の中で、我々中小企業がいかに人材を確保するかを考え、次に取り組んだのがダイバーシティー経営です。男性が多い運輸業界で、優秀なのに子育てや家庭の事情でフルタイム勤務が難しい女性に我が社で働いてもらいたいと考えました。「週の勤務は3日から、1日の就業は4時間から、午前でも午後でも勤務可」という勤務体系を用意したところ、元大手企業勤務で子育て期の女性からたくさんの応募がありました。
現在、女性従業員数は2割を超え、主に安全管理と、ES(従業員満足度)向上の分野で活躍しています。最近では、陶磁器運搬の受注が減少する一方で、瀬戸市では住宅地の開発が進み、また高齢化率(65歳以上の人口の割合)が30%を超える、高い水準にあるという背景から、引っ越しや部屋の片付け、粗大ごみの搬出、生前・遺品整理、震災対策など、地域密着型の業務が増えてきました。高齢者の部屋に入って片付け、不用品を処分し、家具や日用品を再設置する。こうした現場では女性の細やかな気遣いが力を発揮します。「人を仕事に合わせるのではなく、仕事を人に合わせる」。この発想は間違いではなかったと感じます。企業としての付加価値を高めるために多様な視点を取り入れて、さらに雇用の間口を広げています。現在、海外から直接採用した外国人は約10%、障がい者が約5%、さらにLGBTQの社員も複数部署に在籍。個々の特性や得意分野に応じて能力を生かせるように社内環境を整えています。
こうした努力を積み重ねた結果、大学や高校に求人票を出していませんが、7年連続で新卒採用ができています。また、卒論取材のために、弊社に話を聞きたいという大学生や大学院生からの依頼も増えています。取材のテーマは女性活躍・外国人採用・障害者雇用・LGBTQ採用・ダイバーシティー経営・人的資本経営・CSV経営などです。
多様化への対応は良いが、経済的な成長はどう考えるのかと問われることがあります。私も売り上げを上げるために、社員に対して数字の話ばかりしていた時期がありました。しかし、数字を求めるだけでは社員のモチベーションは上がらない。時間がかかっても彼らの満足度を高める。モチベーションや生産性が向上すれば、それが顧客の満足度につながり、企業の業績や利益に結びつく。こうした考えから、自信を持ってダイバーシティー経営に取り組んでいます。
世界が注目する中小企業
私たちが取り組むダイバーシティー経営や健康経営は、短期的には成果は出ません。継続することで組織理解も高まります。これからの地域課題が増える中では、多様な視点が大切な時代です。

健康経営やダイバーシティー経営、地域貢献が認められ数々の賞を受賞。社員のモチベーションにつながっている
少子高齢化が進む中、地域で事業を行う中小企業が果たす役割は、今後さらに大きくなると思います。まずは、健康経営で培ったノウハウを地域社会にも広げたいと考え、健康相談の窓口を地域住民向けに無料で開放しました。行政や地域包括支援センター、病院と協働して、住民に向けた健康セミナーやイベントも実施しています。こうした取り組みを続けたところ、外科学会や看護学会のフォーラムに紹介事例として招かれ、講演する機会が増えました。さらに、生命保険会社をはじめ異業種から事業提携の提案を受けたり、各省庁が主催するアワードで受賞するなど、弊社を取り巻く環境は大きく変化しています。
医療機関や異業種企業との提携は思いがけないシナジー効果を生み、新規顧客の獲得や新たなビジネスモデルの創出など、企業としての可能性を広げてくれます。大橋運輸が業界の枠を越えて新ビジネスに挑戦することで、運輸業界の活性化が進むことも期待できるでしょう。また、このような活動が注目を集めて受賞や取材の機会が増えると、社員のモチベーションアップにもつながります。自分の仕事に誇りを持ち、地域社会に貢献する仕事をもっとしたい、もっと学びたいという意欲が湧いてくるのです。先日、ある障害を持つ社員が「学校での学びが社会で役立つことを母校の生徒に伝えたい」と、自ら進んで提案してくれたときは、思わず胸が熱くなりました。地域に根を張る一中小企業でも、理念を持って行動し続ければ、日本中が、そして世界が注目する魅力的な企業になれると、私は信じています。
動画を見る
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り2551文字 / 全文4922文字

企業情報
- 社名
- 大橋運輸株式会社
- 事業内容
- 一般貨物自動車運送事業・貨物運送取り扱い事業・油脂仕入れ販売・一般廃棄物収集運搬業・産業廃棄物収集運搬業・引っ越しサービス・物流情報サービス・労働者派遣事業・不動産賃貸業・古物売買
- 本社所在地
- 愛知県瀬戸市西松山町2-260
- 代表者
- 鍋嶋洋行
- 従業員数
- 99名(2025年3月時点)