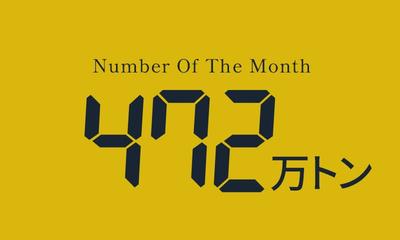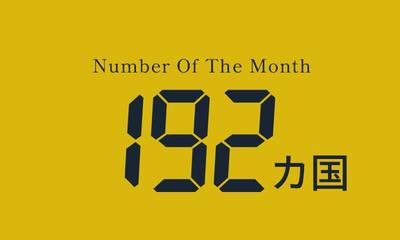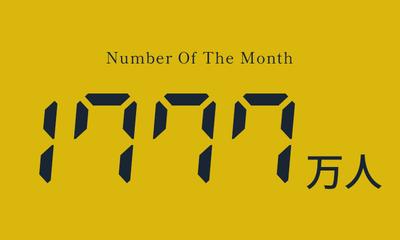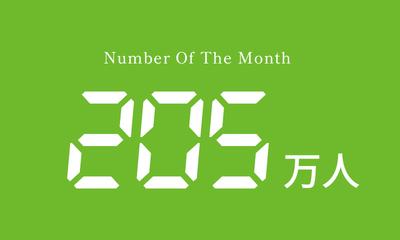トレンドを読み解く今月の数字
ちまたには様々な数字があふれている。それらは時に大きな意味を持つ。
「数字」から世の中の事象を切り取ってみよう。
- 育児休業
- 職場風土の改善
- 人材採用
30.1%
~男性の育児休業取得率~
Number Of The Month
Font "DSEG" by Keshikan. SIL Open Font License 1.1

1992年育児・介護休業法(施行当時は育児休業法)の施行以来、30年が過ぎた。男性の育休取得率は増えないままで推移していたが、2019年頃からコロナ禍を経て上昇傾向になった。24年に発表された厚生労働省の調査(※1)では30.1%と過去最高をマークし、前回(22年)の17.13%から13.0ポイント上昇した。取得期間も延び、1~3カ月未満が最も多く28.0%、2週間~1カ月未満が20.4%で、2週間以上取得する人の割合が増加する傾向にある。育児休業者がいる事業所の割合も、前回調査から13.7ポイント上がり、37.9%と増加した。
男性の育休取得率向上への取り組みは、企業全体にも良い効果を与えるという調査結果もある(※2)。最も高かったのが「職場風土の改善」で56.0%、次いで「従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上」45.9%、「コミュニケーションの活性化」22.6%だった。他にも「離職率の低下」や「新卒・中途採用応募人材の増加」といった人材確保に対する効果も見られ、男性の育休取得は当事者以外の従業員にも良い影響を与えると考えられる。
育休ない企業には就職しない
年代が下がると、育休への意識はさらに大きく変化する。厚生労働省が実施した「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」(※3)は、全国の高校生・大学生などの18~25歳を対象にWebで行われたものだ。同調査によれば、男性の84.3%が育休を取得したいと回答。希望する取得期間は1~3カ月が25.3%となり、半年以上を希望する男性が29.2%と最も多くなった。
育休取得に関する情報は採用面にも影響する。「就職したい気持ちが高まる情報」の1位は、男性の育休取得率だ。育休取得率が高い企業に対して、「安定している」「社員想い」「若手が活躍できる」イメージを持ち、育休取得実績がない企業に対して57.3%の男性が「就職したくない」と回答している。
25年4月には、男性育休取得率向上への取り組み範囲がさらに広がり、育休の取りやすい職場への期待度が高まる。人材確保が深刻化する昨今、企業における男性の育休取得は、人材採用においてこれまで以上に重要なポイントだ。経営者は意識をアップデートする必要がありそうだ。
- ※1令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について
厚生労働省 雇用環境・均等局職業生活両立課 - ※2令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査(速報値)厚生労働省イクメンプロジェクト
- ※3若年層における育児休業等取得に対する意識調査(速報値)厚生労働省イクメンプロジェクト2024年6月実施
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り828文字 / 全文1272文字