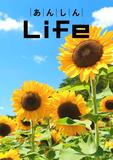藩の育成と繁栄を導いた
伊達政宗を訪ねて
宮城[ 宮城県 ]
- 伊達政宗
- 仙台城
- 瑞巌寺
- 五大堂
- 瑞鳳殿
政治・軍事に優れた手腕を発揮した伊達政宗は
"陸奥の覇者"として知られる名武将だ。
戦国時代から太平の世に向かう中で
仙台藩を創設し発展させた経営者としての顔も持つ。
産業育成・振興のリーダーとしての政宗の足跡を追う。

理想の杜の都を築き
領民の安寧を願う
関ヶ原の戦い後、伊達政宗はかつて

仙台城は最高位標高約131mの高台にある。東と南を
天守を持たないのは、
建物はすべて明治維新の取り壊しや火災、太平洋戦争の空襲で失われ、本丸にあるのは大広間跡の遺構だ。14の部屋から成る大広間は、桃山建築の粋を集めた豪壮華麗な建物だったと伝わる。大広間跡に立つと、ダイナミックなスケールを体感できる。

右/城で唯一の現存建築物である大手門北側土塀。

伊達政宗公騎馬像が立つ本丸北壁石垣から、仙台市内を遠望する。街全体が緑に包まれ、「杜の都」に合点がいく。400年以上前、政宗は家臣に多様な植樹を推奨した。飢餓に備えるためだ。屋敷内には栗、柿、梅などの実がなる木と竹が、隣地との境には杉が植えられた。やがて屋敷林と寺社の林、広瀬川河畔や青葉山の緑は一体となり、杜の都へと発展していく。
政宗は、領民の精神的な拠り所として、神社仏閣の造営にも力を入れた。代表格が、松島にある
瑞巌寺は、平安時代の創建後、

左/本堂と共に国宝に指定される庫裡。堂内へはここから入る
右/参道右側の壁面には、供養塔を彫った洞窟遺跡群が残る
本堂の中心となる

伊達家の藩主が使用した上段の間には、明かり取りの大きな
上段の間に隣接する上々段の間は、皇族を迎えるために造られたと伝わる。明治時代には、明治天皇が東北
本堂の南西端には

右上/文王と呂尚の出会い、周の国都・洛陽の繁栄を描いた文王の間
左下/文王の間の廊下にある扁額には、政宗による寺復興の経緯と意図が記される
右下/欄干に施された彫刻は透かし彫りの「葡萄に栗鼠」
瑞巌寺の境外仏堂である

右/国重要文化財の五大堂。東北地方に残る最古の桃山建築だ

日本三景に数えられる松島の絶景を楽しめるのが、
江戸との交易を実現し
世界へと目を向ける
政宗は、仙台藩の政治の中枢である城と、領民の精神的支柱である社寺を整備した。さらに産業育成・振興に力を注いだ。取り組んだのは経済基盤の核となる農業だ。農作物の栽培に向かない土地に、河川工事や土壌改良を施した。植林による塩害からの防護に努め、新田を開墾した。一方でリスク分散を重視し、気候の影響を受けない鉱山開発、養蚕、砂鉄、和紙などの産業を育成した。
政宗は江戸の人口急増を予測し、さらに大胆な決断をする。江戸との航路がある石巻港を、領地の米を集積する物流拠点とし、大量の米を江戸に輸送・販売したのだ。
石巻は、松島から車で約40分の距離にある。旧北上川の河口付近にある中洲・中瀬は、政宗が米の積み下ろし拠点として港を整備したと伝わる。400年前、仙台藩各地からの舟運や、江戸との交易船でにぎわいを見せたと想像できる。

政宗の目は世界へと向く。ローマ、スペインとの交易のために、藩の総力を上げ、国内最大の帆船「サン・ファン・バウティスタ号」の建造を成し遂げる。典型的なガレオン船だ。ガレオン船とは、19世紀に鉄製蒸気船が登場する以前の遠洋大型船を指す。
仙台藩内の建材を使い、南蛮人の指導のもとで建造された。家臣の
宮城県慶長使節船ミュージアム サン・ファン館では、使節の挑戦の歴史が学べる。以前はサン・ファン・バウティスタ号の木造復元船(原寸大)が係留し、内部公開されていたが、2011年の東日本大震災の津波により損傷する。展示物の多くは流出し、船体の

左/復元船には獅子の造作をはじめ、日本的な装飾も随所に施されている
右/原寸復元船のパーツの展示。船尾に施された伊達家の家紋、九曜紋も巨大だ

右/地球儀を起点にした展示。音と映像で解説する斬新な空間だ
大航海時代を支えたガレオン船の史実は、日本史のみならず世界史の上で重要だ。わけても仙台藩の地元職人も関わって建造された史実は貴重である。同館は2024年のリニューアルオープンにより展示全体が刷新された。音と映像を駆使した没入型展示で学べる。
政宗が夢見た国際交易は、徳川幕府のキリシタン弾圧と鎖国政策により終焉を迎える。当時の航海技術や国際情勢を考慮すれば、政宗の取り組みは極めて先進的な国際思想に基づく快挙だった。
仙台藩の産業・経済・文化の繁栄に尽力した政宗は、1636年に70歳で生涯を閉じた。
政宗の功績に敬意を表し、仙台にある
政宗が眠る

左下/屋根の荷重を支える組物。複雑かつカラフルな様相は類を見ない
右下/扉に施された伊達家の家紋の一つ「竹に雀」。雀の口は阿吽で対をなす
2001年の大規模改修を経て、創建当時の極彩色の威容が再現された。日本史に鮮烈な1ページを残した政宗らしい墓所といえる。江戸時代初期まで、亡くなった主君を家臣が追って自死する殉死の風習があった。政宗の死に際し、家臣15名と家臣に仕えた陪臣5名も殉死する、瑞鳳殿の両脇には供養する石塔が立つ。
戦国時代から江戸時代へと波乱の時代を駆け抜けたリーダー・伊達政宗の偉大さは、宮城県内随所でなお強く感じられる。

右/両脇には殉死者の石塔が、今なお政宗に忠誠を尽くすかのように並ぶ
ちょっと寄り道
鮮度抜群の地魚を堪能
地元松島出身の大将が握る鮨は、すっきりとしたシャリが特徴。鮮度の良いタネのうまさが際立つ。人気は旬の魚を多彩に盛り込んだ「季節の親方おまかせ握り」。取材当日は松島名産の肉厚な穴子を珍しく生で味わえた。脂がのった上品な白身は、平目や真鯛も凌駕するおいしさだ。
■松島 寿司幸
宮城県宮城郡松島町松島字町内88-1
https://t161900.gorp.jp/
- ※リンク先は、予告なく変更になる場合があります

動画を見る
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り5文字 / 全文4814文字




![藩の育成と繁栄を導いた伊達政宗を訪ねて 宮城 [宮城県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/07/thumb_202508-thumb-400xauto-564.jpg)
![維新の立役者・坂本龍馬を訪ねて 高知 [高知県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/06/thumb_202507-thumb-400xauto-542.jpg)
![人材教育を重んじた水戸藩を訪ねて 水戸 [茨城県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/05/thumb_202506-thumb-400xauto-494.jpg)
![希代の名軍師・黒田官兵衛を訪ねて 姫路 [兵庫県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/04/thumb_202505-thumb-400xauto-428.jpg)
![渋沢栄一の郷里を訪ねて 深谷 [埼玉県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/03/thumb_202504-thumb-400xauto-397.jpg)
![横浜の発展に尽くした実業家を訪ねて 横浜 [神奈川県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/02/thumb_202503-thumb-400xauto-340.jpg)
![織田信長の若き日の足跡をたどる 尾張 [愛知県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/01/thumb_202502-thumb-400xauto-318.jpg)
![真田一族の本拠地を訪ねて 上田 [長野県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/12/thumb_202501-thumb-400xauto-295.jpg)
![文豪たちが愛した街を歩く 文京区 [東京都]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202412-thumb-400xauto-108.jpg)
![長州の維新志士を訪ねて 萩 [山口県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202411-thumb-400xauto-57.jpg)
![武田信玄が慈しんだ地 甲府 [山梨県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202410-thumb-400xauto-109.jpg)
![平城京の立役者を訪ねて 奈良 [奈良県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202409-thumb-400xauto-106.jpg)
![足利氏の源流を訪ねて 足利 [栃木県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_20240708-thumb-400xauto-110.jpg)
![明治維新の偉人を訪ねて 鹿児島 [鹿児島県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202406-thumb-400xauto-107.jpg)
![近江商人を訪ねて 近江 [滋賀県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202405-thumb-400xauto-87.jpg)
![徳川家康ゆかりの地 浜松 [静岡県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202404-thumb-400xauto-56.jpg)