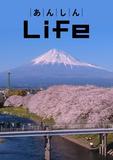日本の常識は世界の常識にあらず
意外と知らない世界の文化
厳しいルールで
国を守るシンガポール

- 国名
- シンガポール共和国
- 面積
- 約720km2
- 人口
- 約564万人(2022年時点)
- 言語
- 国語はマレー語。公用語として英語、中国語、マレー語、タミール語
- シンガポール
- 厳しい罰則
- 合理的政策
- ビジネスの決断力
- 宗教の尊重
この記事のポイント
- シンガポールは多民族・多宗教が共存する都市国家で、観光地としても有名
- 厳しい罰則の背景には、美観や健康、秩序の維持という目的がある
- ビジネスにおけるスピード感と柔軟性は日本人も見習うべき
マレー半島の南端にあるシンガポール共和国は、本島のシンガポール島と大小50ほどの島々からなる都市国家だ。三大民族(中華系、マレー系、インド系)を中心とする多様な民族と宗教が共存し、すべての民族と宗教を平等とする「多人種主義」の理念を掲げている。
年間1千万人以上が来訪する観光大国としても名高い。マーライオン像やシンガポール動物園、ショッピングモールやカジノを有する複合施設「マリーナベイ・サンズ」は、日本人にも人気のスポットだ。街並みがきれいで治安が良く、海外駐在員が暮らしやすい国としても注目を集める。
その一方、注意したいのが罰則だ。シンガポールには法律で定められた厳しい罰則が多く存在する。ひとたびルール違反をすれば、外国人であっても高額の罰金や体罰刑(むち打ち)が科せられる。シンガポールを訪れる際は、どのような罰則があるかをしっかり予習しておこう。
ルールには厳しい罰則が
渡航時に気を付けたいのは、「チューインガム」と「未申告のタバコ」の持ち込みだ。チューインガムは製造、販売が禁止されており、むろん持ち込みも厳禁だ。タバコは1本から課税対象となるため、申告せずに持ち込むとより高い罰金を払わされる。なお、電子タバコについては持ち込みが禁止されているので注意したい。
タバコに関しては、屋内や公共の場は基本的に禁煙だ。屋外でも禁煙の場所が多く、違反すると罰金が科せられる。喫煙者は十分に気を付けよう。電車内での飲食も禁止され、ペットボトルなどで水を飲むのも懲罰の対象となる。
ゴミのポイ捨て、路上にたんや唾を吐く、横断歩道以外の場所で道を渡るといった行為も罰金の対象だ。痴漢の取り締まりも日本よりはるかに厳しく、禁錮刑と体罰刑が執行される。トイレの流し忘れや、水たまりの放置、汚れた車で公道を走ることも厳罰に処される。駐在などで現地に長期間滞在する場合は気を付けたい。
これらの罰則が作られた背景には、それぞれ理由がある。例えば、水たまりはデング熱の媒介となる蚊の発生原因になるので禁止になった。ゴミのポイ捨ては街の美観を保つと同時に、悪質な不法投棄を取り締まる観点から禁止された。タバコの持ち込みは、国民が買いづらいようタバコの高価格を維持する目的があり、禁煙の場所が多いのは国民の健康を維持し医療にかける支出を減らす狙いがある。

シンガポールの地下鉄に掲示された注意書き。地下鉄へのドリアン持ち込みも禁止だ
何より「どんなに小さなルールでも、違反すると厳しく罰せられる」ことを知らしめると、犯罪の抑止や多様な国民の統制に役立つ。シンガポールの"罰則主義"は、多様な価値観を包括しながら安定した秩序を維持する合理的な手段でもある。
変わったルールでは、国内の車の数に上限を設けている点が挙げられる。車の数を少なくし、交通渋滞を防ごうというものだ。車を購入するにはまず車両購入権(有効期間は10年)が必要で、取得はディーラーによる入札方式で行われる。数に限りがある上、レートで相場が変わる。落札には数百万円~数千万円かかる。自由に車を所有できないのは不便だが、バスや鉄道といった公共交通機関が整備され生活にはさほど困らない。この規制のおかげでシンガポールは「国土が狭く人口密度が高いにもかかわらず、渋滞がない国」として国際的に知られる。
何事も合理的
シンガポールが多数の罰則や規制を設けるのは、政治や街づくりを合理的に進める政策の一つといっても過言ではない。その背景にはマレーシアからの独立後、国の存続をかけて経済発展に尽力してきた歴史がある。
独立以前のシンガポールは、マレーシアの豊富な資源を国外へ積みだす商業港に過ぎなかった。1965年にマレーシアから追放される形で独立すると、天然資源や目立った産業がないシンガポールにとって国家存亡の危機となった。
そこで力を入れたのが外資企業の誘致だ。労働組合の活動を制限するなど企業活動に有利な規制を敷く一方で、インフラ整備や税制面の優遇など手厚い支援策を講じて外国企業が参入しやすい環境をつくり上げた。美しい景観の維持を目的とした罰則も、企業誘致を目的としたイメージアップ戦略の一環といえる。
現在のシンガポールの1人当たりのGDPは、日本の2.4倍だ。目覚ましい発展を遂げたのは、国民を「唯一の資源」と捉え、優秀な人材の育成に注力した成果でもある。
シンガポールは厳しい学歴社会で知られる。小学生から成績でクラスを分ける「ストリーミング」が長年行われてきた。現在でも、小学校を卒業する際に受けるPSLE(Primary School Leaving Examination)と呼ばれる全国統一テストの結果で中学校段階でのクラス分けが行われ、ひいては将来が決まるといわれるほどだ。
シンガポールの人は非常に負けず嫌いである。このような性格は中国語方言の「キアス」という言葉で表現される。その傾向は、特に中華系、インド系の人たちに多く見られる。
ビジネスにおいては合理性を感じる場面が多い。分かりやすいのが、決断の速さだ。シンガポールの企業では、部署の担当者に決裁権を与えるケースが多く、交渉の場では迅速に話がまとまりやすい。「持ち帰って検討します」と決断に時間がかかる日本企業より、はるかに効率的といえるだろう。肩書や実績、コネがなくても、良いと感じるものは積極的に取り入れるチャレンジ精神も併せ持つ。スピード感も柔軟性も、ビジネスの成功に欠かせない大切な要素だ。貴重なチャンスを逃さないよう、日本人も大いに見習いたい。
食べ物の話は鉄板
コミュニケーションの話題に困ったときは、食べ物の話をしよう。あいさつ代わりに「スダマカン?」(マレー語で「ごはん食べた?」)と聞くほど、シンガポールの人々は食べるのが大好きだ。「人間は生きるために食べるが、シンガポール人は食べるために生きる」ともいわれる。自分が最近食べたものの話をしたり、一緒に食事をしながら交流を深めたりすると、心の距離が縮まりやすい。
ただし、食のルールや好みは民族や宗教によって様々なので、シンガポール人だからこれがおすすめとは一概に言えない。食事に誘う場合は宗教上の理由などで食べられないものを事前に聞いておきたい。相手の宗教などを聞くことは失礼には当たらない。むしろ、食べられないものを提供してしまう方が失礼に当たるので、遠慮なく聞こう。
シンガポール人は基本的にフレンドリーな気質で、裏表なくはっきりと意見を言う傾向がある。親交の浅い相手に対しても、家族、家賃や給料の金額といった、個人的なことを悪気なく聞いてくる。もちろん、彼らも個人的なことを聞かれても怒らない。逆に、細かく聞くほど「あなたに興味がある」「仲良くなりたい」と意思表示していると捉える。

シンガポールの歴史や文化を理解することは彼らに対するリスペクトとなる。より親しくなるためにも学んでおきたい
より仲良くなるには、民族ごとに異なるパーソナリティーを知っておくと良いだろう。例えば実利的な中華系・インド系の人は、お金の話題を好む。お買い得なセール品や安い店の情報といった、得する情報を共有すると距離を縮めやすい。
マレー系の人はおっとりした傾向で、お金の話はあまり好まない。イスラム教徒が多く、宗教に関する知識を深めておくと交流しやすくなるだろう。
この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。
残り1632文字 / 全文3277文字
市岡 卓
流通経済大学大学院 社会学研究科 教授