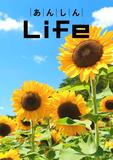日本の常識は世界の常識にあらず
意外と知らない世界の文化
入浴はシャワーのみで湯船につかる文化はない!?
オーストラリア人の
節水ルール、ウソ・ホント
- 国名
- オーストラリア連邦
- 面積
- 768万8287km2
- 人口
- 約2720万人(2024年 豪州統計局)
- 首都
- キャンベラ
- 言語
- 英語
- オーストラリア
- 節水文化
- バーベキュー好き
- 多文化主義
この記事のポイント
- 節水意識は高いが、ネットの極端なルールは誇張も多い。実態はより現実的
- 多文化主義を打ち出したことで先住民へのリスペクトが高まった
- 家族ぐるみでバーベキューに招待するのがオーストラリア流コミュニケーション
オーストラリア連邦は、オーストラリア大陸本土と多数の周辺諸島から成る連邦立憲君主制国家だ。自然豊かな国土には「グレート・バリア・リーフ」やウルル(エアーズ・ロック)を有する「ウルル=カタ・ジュタ国立公園」をはじめ20の世界遺産がある。
国土の大半が乾燥地帯または半乾燥地帯で、特に降水量が少ない内陸部には砂漠も多い。汚水の処理に手間がかかるうえ、10年に一度は大規模な干ばつが起こる。日ごろから水を大事にする習慣が根付く。
子どもの頃から水の使い方に注意を払う教育がなされるほど、オーストラリア人の節水意識は高い。その半面、留学生や移住者向けのサイトには「誇張された節水ルール」の情報が多く掲載されている。キャンベラ、シドニー在住のオーストラリア人の意見を参考に、ネット情報の真偽を検証していこう。
まず「入浴はシャワーのみ。湯船につかる習慣はない」だ。確かにシャワーで済ませる人も結構いそうだが、湯船につかるのを好む人も多い。お風呂グッズもよく売られている。もっとも、スペースの関係で、都市部ではバスタブのないアパートメントが多い。
「シャワーを使う時間が短く、4~5分以内が目安」という説も怪しい。適宜、水を止めながら使ったとしても、十分な時間ではないだろうか。
「毎日髪を洗う習慣がない」も正確には人それぞれだ。オーストラリアにも毎日洗う人は普通にいる。「洗濯はまとめて行う」「洗顔時や手洗い、歯を磨くときは適宜水を止める」もごく普通のことなので、わざわざ取り上げて言うほどではない。「節水の意識を持とう」という印象だ。
「食器洗いはチョロチョロの水量でさっと流す、もしくはペーパーで拭き取る」も一般的とはいえない。今ではオーストラリアの家庭の多くが食器洗浄機を使用し、手洗いよりも使用水量が少ない。汚れをペーパーで拭き取る人は存在するが、これも個人の価値観によるだろう。
「政府が推奨する節水法には『トイレの小は流さない。流すときは大とまとめる』ルールがある」という極端な説もあった。もちろんそんな話は一般的ではない。これは深刻な干ばつのとき、もしくはある砂漠の街で誰かが体験した特殊な事例に尾ひれがついた可能性が高い。
「洗車時はホースの使用禁止」については、深刻な干ばつ時でも、流しっぱなしでなく、ホースの手元にある水を止めるボタンで調整すれば問題ないとされていたようだ。
水に対する規制はオーストラリア全土の共通ルールではなく、州や自治体によって異なることも覚えておこう。オーストラリアでは州の権限が強く、州ベースで独自のルールを定めている。極端なルールを実践すると、逆に現地の人にギョッとされることもあるので、ネットの情報をうのみにしないよう十分に注意しよう。
日本人が知らないオーストラリアの歴史

オーストラリア人と仲良くなるうえで知っておきたいのが、彼らの歩んできた歴史と現在の文化に至るまでの背景だ。
オーストラリアは先住民をはじめ、英国を中心に世界各地からの移民が共生する多民族国家である。国全体の人口比も海外生まれが全人口の3割近くを占め、両親のどちらかが海外で生まれた移民2世も含めると、その割合は5割を超える。
今でこそ誰もが法の下で公平に扱われる「平等主義」(Fair Go)が基本理念とされているが、過去には英国人による先住民への迫害や、非白人の入国制限、在住アジア系住民の国籍取得を困難にする排他的な政策が取られた時代もあった。だが、1970年代に多様な文化を尊重しながら平等な社会を目指す「多文化主義」政策が打ち出されたのを機に、多様な文化や価値観を受け入れ合う意識が醸成されていった。
先住民の土地の所有権をめぐって、92年にオーストラリアの連邦最高裁判所が示した「マボ判決」で、18世紀に植民者の英国がオーストラリアを「無主の地」(所有者のいない土地)として領有したことの正統性を問い、「オーストラリアは先住民の所有する土地だった」と先住権を認めたことも大きな転機だ。これにより、オーストラリアの住民たちは「何万年もこの土地に住み続けた先住民を敬わなければいけない」という考えを共有するようになった。
その一環として行われているのが「アクノレジメント・オブ・カントリー(Acknowledgement of Country)」という、その土地の伝統的な所有者に敬意を表す儀式だ。セレモニーやイベントの開始時に、そこの土地を管理してきた先住民に対する感謝と尊重の言葉を宣言したり、建物の看板およびWebサイトのトップページにメッセージを表示したりして「この土地は先住民のものである」と思い出させる目的がある。
これらに加え、日本人は学校教育で教えられなかったオーストラリアとの戦争の歴史も知っておく必要があるだろう。なぜならオーストラリア人にとって、第2次世界大戦(特に太平洋戦争)は対日戦争として認識されているからだ。オーストラリア本土に爆弾を投下した唯一の国は日本であり、北部の都市ダーウィンには碑が建てられ、日本軍による爆撃の記録が刻まれている。日本軍のオーストラリア人捕虜に対する扱いも非常に過酷だった。オーストラリアの戦災地には慰霊碑が建てられ、日本軍による攻撃の記録が刻まれている。これらの歴史は学校でも教えられ、小説や映画などの題材にもなっている。
現在のオーストラリアは親日国だが、一部には反日感情を持つ人もいる。歴史を知らないと相手に失礼に当たる場合もある。自ら話題に出す必要はないが、相手を敬う礼儀として把握しておくことをおすすめしたい。
人との違いをおおらかに受け入れ合う国民性を持つ

ここからはオーストラリア人の国民性と文化に触れていこう。
オーストラリア人には何気ない会話やちょっとしたジョークを好む明るい気質の人が多い。人への接し方や失敗に対してもおおらかだ。「ごめんなさい」と謝ると「No worries」(ノーウォーリーズ、訳=心配無用、気にしないで)と受け入れてくれる。
親しくなると家族ぐるみで自宅に招くのも彼らの流儀だ。ホームパーティーでもてなし合うのが一般的で、日本のように同僚のみで食事に行くことはあまりない。もし自身がホストを務める場合も、個人ではなく家族単位で招待するのがマナーと心得ておこう。
共に食事を楽しむ際、必ず確認しておきたいのがNG食材の有無だ。オーストラリアの食習慣は多様だからだ。ビーガン、ベジタリアン、豚肉などを禁忌とするイスラム教徒など、制限する食材の基準がそれぞれ違う。事前に「食事で食べられないものはありますか?」と聞くのを忘れないようにしよう。
ヘルシーな食事を好むオーストラリア人の間では、日本食の人気も高い。都市部には地元流にアレンジされたすしやカレーを扱う日本食レストランの数も多く、ツナやアボカドを巻いたのり巻きはコンビニで買える手軽な軽食として親しまれる。
親日国のオーストラリアでは、日本語教育が盛んだ。小学校から日本語を学ぶ機会があり、「花見」や「着物」といった日本の文化にも興味を持つ人は多い。オーストラリアよりも雪質が良いのを理由に、北海道・ニセコへのスキー旅行がはやっている。
日本のアニメや漫画が好きな人も少なくない。シドニーのメインストリートには紀伊國屋書店があり、現地の書籍以外に日本の漫画コーナーも充実している。もし相手がアニメや漫画が好きそうなら、話を振ってみると良い会話のきっかけになるだろう。
会話時に注意したいのは、口元を隠さないことだ。日本人は相手の目を見て話すよう教育されているが、オーストラリアに限らず西洋人はコミュニケーションのときに口元を見る。手で口元を隠したり口を塞いだりするのは失礼な行為に当たるので気を付けよう。
ラフな服装を好み、オフィシャルでもハーフパンツを愛用したり、スーツにビーチサンダルを合わせたりするのもオーストラリア人ならではだ。肌や髪の色が多様だからこそ、それぞれの個性を生かした服装を楽しむ。服装規定もおおらかだ。とはいえセレモニーなどのフォーマルな場ではTPOに合わせた服装を使い分ける。
美しい自然を堪能できるアウトドアレジャーや野外でのバーベキュー(略称:バービー)も人気だ。ソーセージとオニオンがメインという説もあるが、実際はいろいろな肉や具材を焼いて楽しむのが実態だ。真っ先にソーセージが挙がるのは、手軽でおいしいからだろう。
オーストラリアで選挙といえば「デモクラシー・ソーセージ」が有名だ。投票所前にバーベキューの屋台が出て、焼きたてのソーセージを挟んだサンドイッチが売られる。おいしいソーセージを求めて投票所を選ぶ人も多い。オーストラリアでは投票は義務とされる。行かないと原則として罰金を科されるため、毎回9割近い国民が投票に訪れる。
有権者が候補者に順位を付けて投票する「優先順位付連記投票制」が採用されるのも、オーストラリアの選挙の特徴だ。全ての順番を考慮して得票数を決めるので、開票の手間が大きい。全ての結果が出るまでに1カ月以上かかることもある。死票をなくし、できるだけ民意を反映する手段として支持されている。
アフター5はプライベートの時間を大切にする

多様な価値観を持つ人々が暮らすオーストラリアでは、仕事に対する意識も多岐にわたる。多くの人に共通するのは、オンとオフのめりはりがはっきりしていることだ。オーストラリア人は日本人のようにだらだらと残業しない。朝から仕事を始め、仕事の時間が終わったらさっと退社し、家族や友人との付き合いを大切にする。
夏場にサマータイムが導入される州では就業時間が1時間繰り上がる。終業後でも十分に明るく、平日でも近くのビーチに繰り出すケースも珍しくない。
美術館も人々の憩いの場として人気のスポットだ。公立のミュージアムは特別展以外ならたいてい無料で入れる。シドニーのニューサウスウェールズ州立美術館は、なんと水曜日は夜の10時まで開いていて、夕方以降は美術館の中でお酒が飲めるうえ、演奏会や作家のトークショーといった、ちょっとした文化イベントも催される。身近にアートに触れる機会が多いオーストラリア人は、文化に対する感度が高いともいわれる。
我々日本人は世界のさまざまな国々から「働き過ぎ」と言われがちだ。自身をいたわるためにもたまには仕事を早く切り上げて、自然や文化に触れるひとときを持ってみてはいかがだろうか。
飯笹 佐代子
青山学院大学総合文化政策学部 総合文化政策学科 教授